我が家に南部鉄器がやってきた
南部鉄器といわれる伝統工芸品がある。
黒い鋳物でできた重厚なもので、ボツボツとしたあられ模様の鉄瓶などが有名である。
南部鉄器の鉄瓶でお湯を沸かすと「まろやか」になると言われ、鉄器だけに鉄分も多く取れそうなのが魅力だ。
とある縁で南部鉄器の鉄瓶が我が家にやってきた。
アルミやステンレスのやかんとは違う、重厚さだ。
青空に透かして見ても、当然、青空が透けて見えないくらいの鉄の厚みだ。
持ち上げてみると、お・重い。

目の細かな砂で突起となるあられ模様を作り、そこに赤く溶けた鉄を流し込んで作る。
合理化だけでは理解できない、伝統工芸の魅力だ。
購入したのは、南部藩の流れをくむ南部鉄器ではなく、奥州藤原氏から仙台伊達藩の流れをくむ、及源鋳造の南部鉄器だ。
鋳鉄製といえば、キャンプ道具のダッチオーブンも使う前に鍛える必要があるが、南部鉄器の鉄瓶も同様に、使い始めの流儀がある。
これをきちんとしておかないと、錆びたりするのだ。
まず初めにしないといけないのは、鉄瓶の「湯垢づけ」
南部鉄器をはじめて使う前、硬水(硬度300mg)を沸かす「湯垢づけ」という作業が必要になる。
日本のミネラルウォーターの硬度は30~50mg程度なので「軟水」と呼ばれるが、硬度300mg程度のミネラルウォーターを用意しないといけないのだ。
よく知られているフランスのエビアンやヴィッテルがだいたい硬度300mgだ。
近くのスーパーに買いに行ったが、残念ながらエビアンやヴィッテルといった硬水が置いてなく、超硬度のコントレックスしか置いていなかった。
コントレックスは、単なる水ではなく、ダイエット目的などにも使われるものなので、置いていたのかもしれない。
その硬度は、な・なんと1468mgだ。
はじめて飲んでみたが、確かにダイエットに効きそうな感じがする。
少しトロミがあるようなミネラルウォーターだ。

当初は水道水で、硬度が半分くらいになるように薄めて使おうかとも考えたが、しっかりと湯垢を付けるために、そのまま入れて湯垢づくりにチャレンジした。
コントレックスを鉄瓶8分目くらいまで入れ、20分程度沸騰させる。
そして沸かしたお湯を捨て、鉄瓶を余熱で乾燥させる。
これを3回繰り返して、マグネシウムとカルシウムの被膜を鉄瓶内に作るのだ。

今日は涼しい一日だったので、20分見張っていても苦労はなかったが、コントレックスをストレートで入れたことが少し心配だった。
そして最終的に3回沸騰を終え、乾燥させた鉄瓶内部の写真がこれだ。
さすがコントレックス!鉄瓶内は真っ白に湯垢が付いている。

これで準備万端。
これからはこれで水を沸かして、毎日白湯を飲むつもりである。
合理的な暮らしから少しずれた、優雅な暮らしを目指したい。
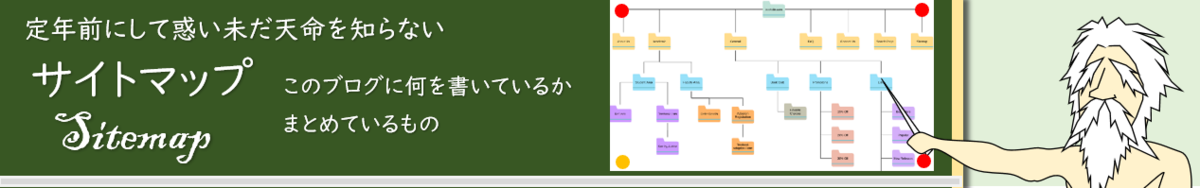 サイトマップ - 定年前にして惑い未だ天命を知らない
サイトマップ - 定年前にして惑い未だ天命を知らない